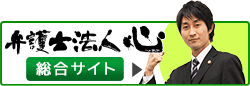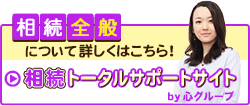今回も本ブログにアクセスしていただき、ありがとうございます。
弁護士・税理士の鳥光でございます。
先日、区分所有建物の自主管理に長年携わり、現場が抱える問題を詳しく知る方とお話をする機会がありました。
区分所有建物は、人口の急増に対応するために作られはじめ、現在2つの老い(建物の老朽化と、住民の高齢化)を迎えていること、現行の制度のもとでマンションを維持管理することは困難になりつつあることなどを聞きました。
このような話は、専門書や区分所有建物に関する記事などで読むことはありましたが、実際に現場で問題に直面している方から聞くのとでは、現実味が全く異なります。
本当に集会で決議をすることができないという事態が発生していることや、集会場で管理費の金額を巡って住民同士の激しい争いに発展する場合があること、マンション管理に関する相談や問題解決の依頼ができる先が少ないことなど、書物からだけでは得られないことをたくさん学ばせていただきました。
また、現状として、区分所有法などマンション管理に関する法規に詳しい人や、マンション管理業務に詳しい人はある程度いるが、相続人不存在などによって管理不全に陥っている区分所有建物への対応に詳しい専門家は、現状として比較的少ないということも知りました。