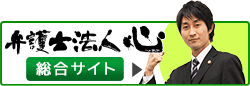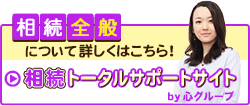本ブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。
弁護士・税理士の鳥光でございます。
今回は、相続財産清算人が管理する財産のなかに、区分所有建物がある場合に確認するべき書類についてです。
まず、管理規約と使用細則です。
前回も少し触れましたが、専有部分と共有部分、駐車場・駐輪場の使用方法(特に使用する際の連絡先)、届出が必要な事項などについて確認します。
管理規約、使用細則について、申立人から引継ぎを受けられなかったり、被相続人の自宅内で発見できなかった場合には、管理組合に連絡をして閲覧をします。
被相続人が敷地内に駐車場や駐輪場を借りている場合があります。
その調査のためには、管理組合に連絡して確認をします。
もし借りている場合には、賃料の支払いをできるだけ早く止めるため、自動車や自転車を売却等したうえで、賃貸借契約を解約します。
自動車や自転車の売却や廃棄の際には、裁判所による権限外行為許可審判が必要となることにも注意が必要です。
相続財産清算人の業務においては、最終的には区分所有建物を売却することになります。
その際には、管理組合に組合員資格喪失届や、区分所有者の変更届を提出する必要があります。
管理規約、使用細則を確認する際、これらの届出についてのフォーマット等があれば確保しておくと売買をスムーズに進められます。