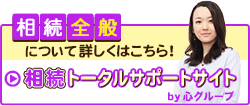今日も本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。
弁護士・税理士の鳥光でございます。
今回は、相続税申告における、未成年者控除について説明します。
未成年者控除とは、相続人が未成年者である場合に、その未成年者の相続税額から一定の額を控除できるという制度です。
未成年者が成人に達するまでの養育費や教育費等を考慮し、税負担を軽減するという趣旨により設けられた制度です。
障害者控除と同じく、課税価格ではなく、相続税額から控除できるという点がポイントで、未成年者の年齢によっては、大きな相続税の軽減効果があります。
相続税額から控除される額は、18歳から相続開始時の年齢(1年未満の端数は切り捨て)を差し引いた数値に10万円を乗じた金額です。
未成年者控除が受けられる人は、次のすべてに当てはまる人です。
1
相続財産を取得した人が法定相続人であること(相続放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)
2
相続開始日に未成年者であること
3
無制限納税義務者であること。
そして、未成年者の相続税額が未成年者控除額より少ない場合には、控除不足額が生じます。
その場合には、不足額は、扶養義務者の相続税額から控除して納付することができます。